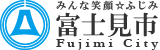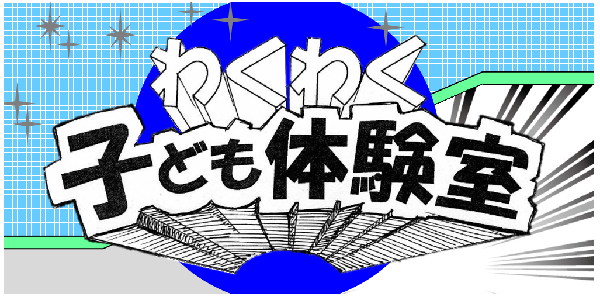わくわく子ども体験室
最終更新日:2025年3月31日
わくわく子ども体験室とは…?

子どもたちの休日を有意義なものにするきっかけづくりとして、様々な実験・製作の場を提供しています。
自分で製作し体験することにより、新たな発見・好奇心の育成・自ら学ぶ心を養うことを目的にしています。
令和7年度の開催
夏休みにわくわくする体験をしようと計画中です。お楽しみに!
令和6年度の開催
『木の香りの貯金箱』7月23日
牛乳パックを再利用した貯金箱を作りました。指導は飯島紀さんです。
まずは、ものさしで線を引き、はさみで切って家の形の貯金箱のベースを作ります。
壁と屋根の形ができたら、壁紙を貼っていきます。高学年は両面テープを貼るところからやってみます。
柳・竹・桜などの小枝をボンドで貼ります。窓やドアを作ったり、壁一面を小枝で埋めたりと、オリジナルの家を作りました。
『ペットボトルキャップで作るエコチャーム』7月25日
ペットボトルキャップを材料にしたエコチャームと、余った毛糸を再利用したタッセルを作りました。指導は小山由佳さんです。
ペットボトルキャップは、はさみでりんごの皮をむくように切っていき、袋の中で細かく切ります。フレームに細かく切ったものを山盛りに入れて、クッキングシートを被せます。
ゆっくりとアイロンを置き、キャップが溶けるのを待ちます。両面ともかけたら、冷めるまで待ってから、はみ出た部分を取ってきれいにします。余った毛糸は好きな色を選んで段ボールに巻いて、タッセルを作ります。
エコチャームとタッセルに丸カンを付けて、カニカンに付けたら完成!グラデーションやマーブル模様が素敵な、世界に1つだけのチャームができました。最後はみんなでピースの星マーク★
YouTubeで作り方をご覧になれます
- 【工作】エコチャーム作り(1)//ペットボトルキャップと余った毛糸で作る
- 【工作】エコチャーム作り(2)//ペットボトルキャップと余った毛糸で作る
『スーパーボール作り実験』7月29日
手作りのスーパーボール作り実験を行いました。指導は富士見高校理科部の生徒さんたちです。
自由研究として、まずは予想やきっかけを実験用紙に記入します。はじめに計りを使って塩を計り、そこに軽量カップで計った水を入れ、好きな色を足して混ぜます。
洗濯のりを計り、好きなラメを入れて混ぜます。そこに、飽和食塩水を一気に入れて、やさしく混ぜると…割りばしにかたまりが付きました。これがスーパーボールの素です。
手についた水分をタオルで取りながら丸めていき、完成!では、どうして固まったのか?理科部の生徒さんから答えを聞き、実験用紙にまとめや感想を書きました。
令和5年度の開催
『スパッとクルッとエコバッグ』7月26日
たたむときはサッと小さくなるエコバッグを、手縫いで作りました。指導は小山由佳さんです。針に糸を通し、玉止め・玉結びの練習をしてから始めます。アイロンで折り目を付けたら、2か所直線縫いをします。
持ち手のバンドを通して一緒に縫うのが硬くて大変…。気を付けながらみんな頑張りました。バイアステープを端に付けて、もう一息だ!
クルミボタンも自分で作り、縫い付けます。完成したときは、縫うのが大変だったけど達成感があった、と感想を話してくれました。
『エコな真夏のスノードーム』7月28日
午前の部
午前の部と午後の部の2回開催しました。午前は佐伯さゆりさんに指導をしてもらいました。フィギュアや造花のどれを入れようか、どこに置こうか迷っちゃいますね。配置が決まったらグルーガンで接着してもらいます。
ラメとのりの入った水をそーっと入れて完成!
午後の部
小嶋由香利さんに指導をしてもらいました。配置を決めてグルーガンで接着したら、中に入れるラメとホログラムを選びます。
のり水を入れて蓋をして、お花紙をかぶせてと紙リボンを巻いて完成!リボンの巻き方は上級生が下級生に教えてくれました。
スノードーム作品の一部を紹介します。
令和4年度の開催
『牛乳パックのからくり貯金箱』7月27日
牛乳パックを使って、コインがコロコロ転がるからくり貯金箱を作りました。牛乳パックをはさみで切ることが硬くて大変だったけど、クラフトテープを貼ったり、みんな集中してがんばりました!指導は柳下裕美さんです。
『保冷剤の消臭フレグランス』7月26日
夏休みに再利用を楽しく学べる工作ができて、SDGsを意識する体験になったと思います。保冷剤を使って、涼しげで爽やかな消臭芳香剤を作りました。指導は三塚好江さんです。
『空き缶リメイク&ハーブ』開催 6月18日
空き缶にクールなペイントをして、チャイブやローズマリー・バジル・パセリなどの料理に使えるハーブを2種類植え、父の日のプレゼントに。お肉料理やキャンプで大活躍!
指導は小嶋由香利さん。まずは、空き缶にひげマークの型紙を貼って、ステンシルペイントをします。
水捌けをよくするために鉢底に赤玉土を入れ、ハーブを寄せ植えします。土がしっかりと入るように、割りばしで土を数か所つつきます。ネームプレートを刺して、父の日のメッセージカードを書きます。
育て方のプリントと一緒にラッピングします。実用的でカッコイイ作品ができました!お父さん喜んでくれるかな?
みつろうラップ作り 5月7日
繰り返し使える自然素材の布ラップを手作りして、母の日にプレゼントしよう!環境にやさしく、毎日の生活がちょっと華やかになるグッズです。
教えてくれるのは飯島のりさんです。好きな布を選んだ後、作り方を見ながら布にみつろうチップを並べていきます。
3・4年生は15cm×15cmの四角と丸を、5・6年生は15cm×15cmと30cm×30cmの2サイズの四角を作ります。アイロンは上から乗せるように置いて、みつろうを溶かします。
5・6年生は家庭科やお手伝いでアイロンを使ったことがあるので、慣れた様子。大きいサイズも丁寧にかけていきます。また、アイロンの順番待ちの間には、母の日の手紙やカードを書きました。ラッピングの仕方も教えてもらい、取扱説明書と手紙を一緒にラッピングして、完成です!
令和3年度の開催
今回は、ボッチャ体験、木で作ろうビー玉迷路、フェルトソープ作りの3つの内容を行いました。
(感染症防止対策のため、例年より定員を少なくした上での開催となりました)
ボッチャ体験【7月27日開催】
ボッチャは、ジャックボールと呼ばれる白いボールに赤・青のそれぞれ6球ずつのボールを投げ、いかに近づけるかを競う競技です。ルールはとても簡単で、だれでも楽しめますが…先を読む頭脳戦でもあります!緻密(ちみつ)な戦略と駆け引きが、競技をする人も見る人も熱くします…!指導は、スポーツ推進委員(南畑小学校区)の長堀さん、柳川さん、新井さんです。
まずは、ルールについて説明を受けます。ボールを持ってみると、思っていたよりも重くて、弾まない?でも転がる…今までに経験したことのない感触です。
チームに分かれて試合開始!4チームで総当たり戦をしました。
ジャックボール(白いボール)からいちばん近いボールが赤の場合は、青のボールを持っているチームが次に投げます。勝敗は、どっちかな?コンパスを使って、ジャックボールからの距離を比べてみよう。
木で作ろう ビー玉迷路【7月28日開催】
木のぬくもりを感じながら、いろんな形の木(端材)をはり、ビー玉をスタートからゴールまで運ぶ迷路を作ります。なかなかゴールにたどり着けない迷路になるのか!?みんな自分だけのオリジナル迷路を完成させました。指導は小嶋由香利さんです。
初めはボンドは使わず、端材をどんどん置いて、ビー玉が通る迷路を作っていきます。どんな形にしようか迷いますね。
細かい端材を追加して、だんだんと形が定まってきました。なんだか、近未来都市のような作品も。
場所が決まったら、端材にボンドを薄くつけて、台になるパネルに付けていきます。ここまできたらラストスパート!フラッグを足して、完成ー!
フェルトソープ【7月30日開催】
せっけんに羊毛を巻いたフェルトソープは、見た目もかわいく・触り心地も良い、毎日の手洗いを楽しくしてくれるせっけんです。もちもち・フワフワな泡ができます。指導は小山由佳さんです。
始める前に、先生のデモンストレーションをみて、流れを確かめます。好きな色の羊毛3色を決めたら、まずはベースとなる羊毛をせっけんに巻いていきます。
次に、模様用の羊毛をのせていきます。模様ができたら、お湯を注いで、ひたすた両手で擦ります!!
できたかな?触って羊毛が固く(フェルト化)なったか確かめます。できたら、水でサッと泡を流して完成!色とりどりの、楽しいソープが出来上がりました。
令和2年度の開催
今回の夏休みは例年に比べ短いですが、短い夏を有意義な日々にする2種類の工作を用意しました。
アロマワックスサシェ作り 7月29日開催
牛乳パックの型に流したワックス(ろう)に、好きな飾りと、香りをほんのりつけたサシェを作りました。指導は三塚好江さんです。
まずは、3種類のアロマオイルの香りをかいで好きなものを選びます。そして、キャンドルをホルダーから外して溶かす準備をします。
ろうに色を付けるために、クレパス(クレヨン可)を削ります。また、型の中に好きな飾りを置いていき、イメージを膨らませ位置を決めます。海にしようか…?花にしようか…?悩みますよね。
飾りをいったん取り出しておき、湯せんにかけたろうに、削ったクレパスとアロマオイルを入れてよく混ぜます。それを型に流して、表面が固まってきたら、飾りを手早く置いていきます。そして、ヒモを通す位置にストローを刺します。
固まるまで1日置いたら、仕上げ作業。型から外し、形を整えて、ヒモを通して、ラッピングして…。
ほのかに香る、夏らしいさわやかなアロマワックスサシェの完成です!みんな完成度が高い!!玄関やクローゼットに飾って楽しんでくださいね。
小枝のフォトフレーム作り 8月3日開催
小枝を使ったナチュラルなフォトフレームを作りました。指導は渋谷真実さんです。
今回用意した枝は、さくら・やなぎ・ゲッケイジュの三種類。色や手触りがそれぞれ違いますね。まずは、小枝を枠に置いていき、デザインを決めます。
1種類を縦横交互に並べたり、3種類を混ぜて置いてみたり。みんな個性があって面白いですね。だいたいの位置が決まったら、ボンドで貼っていきます。
小枝を貼り終わったら、フレーム枠を台紙に貼ります。角を合わせてそーっと。
裏面にスタンドを付けて完成!! 大切な夏の思い出や、大好きなペットの写真を入れて飾ってくださいね。