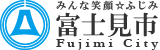予防接種
最終更新日:2025年8月14日
予防接種とは
予防接種とは、病気に対する免疫をつけたり、免疫を強くするために、ワクチンを接種することをいいます。
ワクチンを接種した方が病気にかかることを予防したり、人に感染させてしまうことで社会に病気がまん延してしまうのを防ぐことを主な目的としています。
また、病気にかかったとしても、ワクチンを接種していた方は重い症状になることを防げる場合があります。
定期予防接種とは
予防接種法に基づき、国や自治体が実施している(接種することを勧奨している)予防接種で、対象年齢や接種回数(間隔)などが定められています。
法律で定められている子どもの定期予防接種は、無料(公費負担)で受けることができます。
任意予防接種とは
予防接種法に定められていないため、被接種者もしくは保護者の判断で受ける予防接種です。
接種する際は、医師とよく相談しましょう。接種費用は有料(自己負担)です。
予防接種の効果や安全性のためにも、対象者や接種内容等を正しく理解し、予防接種を受けましょう。
定期予防接種
ワクチンには標準的な(望ましい)接種間隔があります。可能な限り標準的な接種間隔で接種しましょう。
接種対象者
接種日に富士見市に住民登録のある方
(注記)予防接種の種類により、対象年齢等が異なります。
料金
無料
(注記)対象年齢や、定められた接種回数や接種間隔を外れた接種については、有料(自己負担)となります。
接種場所
医療機関での個別接種
定期予防接種実施医療機関(富士見市・ふじみ野市・三芳町)
富士見市・ふじみ野市・三芳町以外の医療機関で予防接種を希望する場合
富士見市・ふじみ野市・三芳町の実施医療機関以外で予防接種を希望する場合、医療機関の所在地によって対応が異なります。
詳細は「富士見市・ふじみ野市・三芳町以外の医療機関で予防接種を希望する方へ」をご覧ください。
持ち物
- 母子健康手帳(注記1)
- 予診票(注記2)
- マイナンバーカード等健康保険の資格が確認できる書類またはこども医療費受給資格証
(注記1)母子健康手帳をお持ちでない方は、予防接種済証を医療機関から受け取り、大切に保管してください。
(注記2)予診票は出生届を提出した際にお渡しした予防接種手帳を使用してください。転入された方や紛失した場合は実施医療機関にも在庫がありますので、そちらを使用してください。
定期予防接種一覧
予防接種法に関する法律の一部改正により、令和6年10月1日から小児用肺炎球菌の予防接種で使用しているワクチンに、『沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン』に変更になります。
なお、令和6年4月1日から定期接種に追加された『沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン』も当面の間使用できます。
ワクチンの種類(15価・20価)で対象年齢や接種間隔に違いはありません。
詳しくは![]() 子どもの肺炎球菌ワクチン(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)をご参照ください。
子どもの肺炎球菌ワクチン(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)をご参照ください。
[対象者と接種内容]生後2か月から5歳に至るまで (注記)接種開始年齢によって接種回数が異なります。
| 対象(接種開始)年齢 | 回数 | 接種内容(接種間隔) | |
|---|---|---|---|
| 生後2か月から7か月に至るまで(標準的な接種開始年齢) | 4回(初回3回、追加1回) | 初回 | 1回目 |
2回目:1回目から27日以上の間隔をおいて接種 | |||
3回目:2回目から27日以上の間隔をおいて接種 | |||
| 追加 | 追加:3回目から60日以上の間隔をおいて1歳以降に接種 | ||
| (注1)2回目・3回目は2歳に至るまでに接種し、それを超えた場合は接種しないこと(追加接種は可能)。また、2回目が満1歳を超えた場合は3回目は接種しないこと(追加接種は可能) | |||
| 生後7か月から1歳に至るまで | 3回(初回2回、追加1回) | 初回 | 1回目 |
2回目:1回目から27日以上の間隔をおいて接種 | |||
| 追加 | 追加:2回目から60日以上の間隔をおいて1歳以降に接種 | ||
| (注2)2回目の接種は2歳に至るまでに接種し、それを超えた場合は接種しないこと(追加接種は可能) | |||
| 1歳から2歳に至るまで | 2回(初回1回、追加1回) | 初回 | 1回目 |
| 追加 | 追加:1回目から60日以上の間隔をおいて接種 | ||
| 2歳から5歳に至るまで | 1回 | 1回のみ | |
[対象者と接種内容]
| 対象年齢 | 回数 | 接種内容(接種間隔) |
|---|---|---|
| 1歳に至るまで | 3回(注記) | 1回目:標準的な接種時期は生後2か月に至った時から生後9か月に至るまでの期間 |
| 2回目:1回目の接種後、27日以上の間隔をおいて接種 | ||
| 3回目:1回目の接種から139日以上の間隔をおいて接種 | ||
| 1回目の接種から3回目の接種を終えるまでには、おおよそ半年間かかります。1歳になってしまうと、定期接種の対象外となりますので、スケジュールをよく確認して予防接種を受けるようにしてください。 | ||
(注記)すでにB型肝炎ワクチンを接種した回数分(任意接種も含む)を除きます。また、母子感染予防として、出生後すぐにB型肝炎ワクチンの接種を受けたお子さんも除きます。
予防接種法の改正により、令和2年10月1日からロタウイルスワクチンが定期接種になりました。
[対象者と接種内容]
| ワクチン種類 | 対象年齢 | 回数 | 接種内容(接種間隔) |
|---|---|---|---|
| 1価ワクチン(ロタリックス) | 生後6週から | 2回 | 標準的な初回接種は生後2か月から生後14週6日までに実施 |
| 5価ワクチン(ロタテック) | 生後6週から | 3回 | 標準的な初回接種は生後2か月から生後14週6日までに実施 |
標準的な初回接種期間:いずれのワクチンも生後2か月から生後14週6日までに実施。 | |||
(注1)最初に接種したワクチンを2回目以降も接種します。途中からワクチンの変更はできません。
(注2)いずれのワクチンも初回接種は生後14週6日までに実施してください。生後15週以降の初回接種は週齢が高くなるにつれて自然発症による腸重積症のリスクが増加するので、お勧めできません。
五種混合(DPT-IPV-Hib)
百日せき・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ
予防接種法に関する法律の一部改正により、令和6年4月1日に定期接種に追加されました。
[五種混合の対象者と接種内容]
| 対象年齢 | 回数 | 接種内容(接種間隔) | |
|---|---|---|---|
| 生後2か月から7歳6か月に至るまで | 1期初回(注記) | 3回 | 1回目 |
2回目:1回目から20日以上の間隔をおいて接種 | |||
3回目:2回目から20日以上の間隔をおいて接種 | |||
| 1期追加 | 1回 | 追加:1期初回の3回目接種後6か月以上の間隔をおいて接種 | |
(注記)1期初回の標準的な接種年齢は、生後2か月から生後7か月までです。 | |||
四種混合(DPT-IPV)
百日せき・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ
令和6年4月より、四種混合ワクチンを含む五種混合ワクチン(四種混合ワクチン+ヒブワクチン)が新たに定期予防接種に加わりました。
すでに四種混合ワクチンを接種し、全回数の接種を完了していないお子様におかれましては、五種混合ワクチンではなく四種混合ワクチンとヒブワクチンそれぞれの接種を推奨しておりますが、四種混合ワクチンの販売中止により四種混合ワクチンの接種が受けられない場合、ヒブワクチンの接種回数にかかわらず、五種混合ワクチンの接種を受けることが可能です。
[四種混合の対象者と接種内容]
| 対象年齢 | 回数 | 接種内容(接種間隔) | |
|---|---|---|---|
| 生後2か月から7歳6か月に至るまで | 1期初回(注記) | 3回 | 1回目 |
2回目:1回目から20日以上の間隔をおいて接種 | |||
3回目:2回目から20日以上の間隔をおいて接種 | |||
| 1期追加 | 1回 | 追加:1期初回の3回目接種後6か月以上の間隔をおいて接種 | |
(注記)1期初回の標準的な接種年齢は、生後2か月から1歳です。 | |||
三種混合(DPT)ワクチン
三種混合の接種が規定回数(1期初回3回、追加1回)を完了していない場合は、四種混合を接種してください。
使用するワクチン等についての詳細は、![]() 「ポリオとポリオワクチンの基礎知識」「ポリオワクチンに関するQ&A」(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)をご覧ください。
「ポリオとポリオワクチンの基礎知識」「ポリオワクチンに関するQ&A」(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)をご覧ください。
詳しくは、かかりつけ医師または健康増進センターにご相談ください。
ポリオの予防接種は、平成24年9月1日から生ポリオワクチンの定期予防接種が中止になったことにより、単独の不活化ポリオワクチンが定期の予防接種に変わりました。
[対象者と接種内容]
| 対象年齢 | 回数 | 接種内容(接種間隔) | |
|---|---|---|---|
| 生後2か月から7歳6か月に至るまで | 1期初回(注記) | 3回 | 1回目 |
2回目:1回目から20日以上の間隔をおいて接種 | |||
3回目:2回目から20日以上の間隔をおいて接種 | |||
| 1期追加 | 1回 | 追加:1期初回の3回目接種後6か月以上の間隔をおいて接種 | |
| (注記)1期初回の標準的な接種年齢は、生後2か月から1歳です。 | |||
過去に生ポリオワクチンを接種していない方も、対象年齢内であれば不活化ポリオの定期接種を受けることができます。
注意事項
- 生ポリオワクチンを1回接種した方は、不活化ポリオワクチンを3回接種します。
- 生ポリオワクチンを2回接種した方は、不活化ポリオワクチンの接種は不要です。
- 海外などですでに不活化のポリオワクチンを1回から3回接種している方は、不足回数分の接種を受けることができます。
- 原則として、最初に使用した不活化ポリオワクチン(四種混合または単独の不活化ポリオ)を最後まで使用することが望ましいですが、三種混合の接種が規定回数を完了していない場合は、四種混合ワクチンを接種してください。
使用するワクチン等についての詳細は、 「ポリオとポリオワクチンの基礎知識」「ポリオワクチンに関するQ&A 」(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)をご覧ください。
「ポリオとポリオワクチンの基礎知識」「ポリオワクチンに関するQ&A 」(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)をご覧ください。
詳しくは、かかりつけ医師または健康増進センターにご相談ください。
令和6年4月より、四種混合ワクチンを含む五種混合ワクチン(四種混合ワクチン+ヒブワクチン)が新たに定期予防接種に加わりました。
ただし、すでにヒブワクチンを接種し、全回数の接種を完了していないお子様におかれましては、五種混合ワクチンではなく四種混合ワクチンとヒブワクチンそれぞれの接種を推奨しています。
[対象者と接種内容]生後2か月から5歳に至るまで (注記)接種開始年齢によって接種回数が異なります。
| 対象(接種開始)年齢 | 回数 | 接種内容(接種間隔) | |
|---|---|---|---|
| 生後2か月から7か月に至るまで(標準的な接種開始年齢) | 4回(初回3回、追加1回) | 初回 | 1回目 |
| 2回目:1回目接種後27日以上の間隔をおいて接種(注1) | |||
| 3回目:2回目接種後27日以上の間隔をおいて接種(注1) | |||
| 追加 | 追加:3回目接種後7月以上の間隔をおいて接種 | ||
| (注1)2回目・3回目は1歳に至るまでに接種し、それを超えた場合は接種しないこと。この場合、追加接種は可能ですが、初回接種の最後の接種終了後27日(医師が認めた場合は20日)以上の間隔をおいて1回接種 | |||
| 生後7か月から1歳に至るまで | 3回(初回2回、追加1回) | 初回 | 1回目 |
| 2回目:1回目接種後27日以上の間隔をおいて接種(注2) | |||
| 追加 | 追加:2回目接種後7か月以上の間隔をおいて接種 | ||
| (注2)2回目は1歳に至るまでに接種し、それを超えた場合は接種しないこと。この場合、追加接種は可能ですが、初回接種の最後の接種終了後27日(医師が認めた場合は20日)以上の間隔をおいて1回接種 | |||
| 1歳から5歳に至るまで | 1回 | 1回のみ | |
[対象者と接種内容]
| 対象年齢 | 回数 |
|---|---|
1歳に至るまで(注記) | 1回 |
(注記)標準的な接種年齢(期間)は生後5か月から8か月に至るまでです。早期(3か月未満)に接種した場合、極めて少数ですが、重い副反応を起こす危険性があります。接種時期については、医師と相談してから決めましょう。
[対象者と接種内容]
| 対象年齢 | 回数 | |
|---|---|---|
| 1期 | 1歳から2歳に至るまで | 1回(注記) |
| 2期 | 小学校就学前の1年間(4月1日から翌年3月31日まで。いわゆる年長相当) | 1回(注記) |
(注記)すでに麻しんまたは風しんにかかったことのある子は、1期および2期ともに、かかっていない方の単抗原ワクチンを接種することも可能です。
麻しん風しん混合(MR)ワクチン定期接種の期間延長について
令和6年度に麻しん風しん混合(MR)ワクチンの一時的な供給不足が生じたことに伴い、令和6年度中に接種を行うことができなかった以下の方を対象に、定期接種の期間(無料で接種できる期間)を2年間延長します。
対象者
麻しん風しん1期
令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの方(令和7年度に満3歳に達する方)
麻しん風しん2期
平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの方(令和7年度に小学校1年生にあたる方)
接種延長期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間
[対象者と接種内容]
| 対象年齢 | 接種回数 | 接種内容(接種間隔) |
|---|---|---|
| 1歳から3歳に至るまで | 2回 | 1回目:標準的な初回接種時期は1歳から1歳3か月に至るまで |
2回目:1回目接種後、3月以上の間隔をおいて接種 |
[対象者と接種内容]
| 対象年齢 | 回数 | 接種内容(接種間隔) | |
|---|---|---|---|
| 生後6か月から7歳6か月に至るまで | 1期初回 | 2回 | 1回目 |
2回目:1回目から6日以上の間隔をおいて接種 | |||
1期追加 | 1回 | 追加:1期初回の2回目接種後6か月以上の間隔をおいて接種 | |
| 9歳から13歳未満 | 2期 | 1回 | 乳幼児期の追加として1回接種 |
日本脳炎予防接種の受け方や特例対象者など、詳しくは日本脳炎予防接種についてをご覧ください。
二種混合(DT)
ジフテリア・破傷風
[対象者と接種内容]
| 対象年齢 | 回数 | 接種内容 |
|---|---|---|
| 11歳から13歳未満 | 1回 | 乳幼児期に接種した三種混合または四種混合の追加として1回接種(注記) |
| (注記)乳幼児期に三種混合または四種混合を3回以上接種していない場合は、1回の接種では免疫ができませんので追加の接種が必要になります。(この場合は自費になります。) | ||
令和3年11月26日より、積極的な接種勧奨を控える勧告が廃止されました
ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)ワクチンについては、平成25年6月14日付厚生労働省の通知に基づき積極的勧奨を差し控えておりましたが、令和3年11月26日付厚生労働省の通知により、積極的な接種勧奨を控える勧告が廃止されました。
詳細は「ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)ワクチンについて」をご覧ください。
[対象者と接種内容]
| 対象年齢 | 回数 | 接種間隔 |
|---|---|---|
小学校6年生から高校1年生相当の年齢の女子(注1) | 3回 | 1回目 |
| 2回目:1回目から1か月以上の間隔をおいて接種 | ||
| 3回目:1回目から6か月以上の間隔をおいて接種 | ||
| ただし、当該方法をとることができない場合は、1か月以上あけて2回目を接種した後、1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて3回目を接種。 | ||
| 対象年齢 | 回数 | 接種間隔 |
|---|---|---|
小学校6年生から高校1年生相当の年齢の女子(注1) | 3回 | 1回目 |
| 2回目:1回目から2か月以上の間隔をおいて接種 | ||
| 3回目:1回目から6か月以上の間隔をおいて接種 | ||
ただし、2回目が当該方法をとることができない場合は、1回目の接種から少なくとも1か月以上の間隔をおいて接種。 | ||
シルガード9(9価ワクチン)
令和5年4月よりシルガード9(9価ワクチン)が定期接種に追加されました。
| 対象年齢 | 回数 | 接種間隔 |
|---|---|---|
| 小学校6年生から15歳の誕生日の前日までの女子(注1) | 2回 | 1回目 |
| 2回目:1回目から6か月以上の間隔をおいて接種 | ||
1回目の接種日時点で15歳未満の場合、2回で接種完了。 | ||
| 15歳以上で高校1年生相当までの女子(注1) | 3回 | 1回目 |
| 2回目:1回目から2か月以上の間隔をおいて接種 | ||
| 3回目:1回目から6か月以上の間隔をおいて接種 | ||
1回目の接種日時点で15歳以上の場合、3回で接種完了。 | ||
(注1)標準的な接種年齢は中学校1年生です。学年の表記で「相当」とは、その学年の年齢に該当する方を対象者としています。
(注2)HPVワクチンの接種は、原則、同じ種類のワクチンを受けることをお勧めしますが、過去にサーバリックス(2価ワクチン)またはガーダシル(4価ワクチン)の接種を受けて、3回の接種が完了していない方には、シルガード9(9価ワクチン)との交互接種が認められます。シルガード9(9価ワクチン)の接種を検討している方は医師にご相談ください。
平成9年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた方のHPVワクチン接種について
対象年齢等の数え方
予防接種の対象年齢は民法をもとに計算しています。民法では誕生日の前日に年齢が加算されます。
対象年齢の「○○歳(か月)に至るまで」「○○歳(か月)未満」「○○歳(か月)に達するまで」とは、○○歳(か月)になる前日(1日前)までになります。
対象年齢、接種回数(間隔)を外れると定期外接種となり、有料(自己負担)になりますので、ご注意ください。
長期療養等の特別な事情の方へ
定期予防接種の対象者であった期間に、長期療養を必要とする疾病にかかったなど特別な事情により、やむを得ず定期予防接種の機会を逸した方について、その機会が確保され、定期予防接種として接種できます。(予防接種法の改正により、平成25年1月30日から適用)
適用される期間は、特別な事情がなくなった日から2年を経過するまでの間です。(ただし、予防接種の種類により年齢の上限があります)
特別な事情とは、下記の理由に該当する方です。
- 重症複合免疫不全症等免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病にかかった方
- 白血病等免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病にかかった方
- 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方
- 医学的知見に基づき、上記理由に準ずると認められる方
詳しくは、健康増進センターへお問い合わせください。
予防接種を受ける前の注意事項
- お子さんが健康で体調の良い時に受けましょう。
- 接種予定の予防接種について、必要性や副反応などについて理解しましょう。
- 接種に行く前に必ず体温を測定し、平熱であることを確認しましょう。
- お子さんの健康状態をよく知っている保護者の方が必ず付き添いましょう。
- 接種前や日常の健康状態を、医師に詳しく説明しましょう。
- 分からないことは、接種を受ける前に接種医師に相談しましょう。
予防接種が受けられないとき
- 明らかに発熱している(通常、体温が37.5度以上)とき。または、発熱し熱が下がってから2週間たってないとき
- ひきつけを起こして1年経過していないとき(単純な熱性けいれんの場合は、3か月経過していれば受けられます)
- 麻しん、風しん、水痘、おたふくかぜ、インフルエンザなどにかかり、治ってから4週間経過していないとき
- 中耳炎、急性扁桃腺炎、溶連菌感染症、突発性発疹にかかり、治ってから2週間経過していないとき
- 受けようとする予防接種の接種液の成分により、アナフィラキシー(注1)を起こしたことがあるとき
- その他、医師が不適当な状態と判断したとき
- 1か月以内に家族や友達に、麻しん、風しん、水痘、おたふくかぜなどの病気の方がいた場合は、事前に医師または健康増進センターにお問い合わせください。
(注1)「アナフィラキシー」とは、接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことで、汗がたくさん出る、顔が急に腫れる、全身にひどいじんましんが出るほか、はきけ、嘔吐、声が出にくい、息が苦しくなる、などの症状に続きショック症状が出るような、激しい全身反応のことをいいます。
予防接種を受けた後の一般的な注意事項
- 予防接種を受けたあと30分間程度は、医療機関でお子さんの様子を観察するか、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。急な副反応が、この間に起こることがまれにあります。
- 接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意しましょう。
- 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
- 当日は、激しい運動はさけましょう。
- 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。
予防接種(感染症)に関する情報
予防接種による健康被害救済制度について
予防接種法に基づく定期予防接種により健康被害が生じた場合には、健康被害を救済する制度があります。健康被害が予防接種によるものであると認定された場合に給付を受けることができます。
また、予防接種法に基づかない任意の予防接種により健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による「医薬品副作用被害救済制度」「生物由来製品感染等被害救済制度」に基づく救済の制度があります。
「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」に基づく接種に係る医薬品副作用被害救済制度について
平成23年2月1日から平成25年3月31日までの間に、富士見市の助成(「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」に基づく接種)により、「子宮頸がん予防ワクチン(ヒトパピローマウイルスワクチン)」「ヒブワクチン」「小児用肺炎球菌ワクチン」のいずれかを接種した方のうち、接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。
お心当たりのある方は、具体的な請求方法等について、![]() 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度相談窓口(外部サイト)にお問い合わせください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度相談窓口(外部サイト)にお問い合わせください。
お問い合わせ
健康増進センター 保健予防係
〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬3351番地の2
電話番号:049-252-3771
FAX:049-255-3321