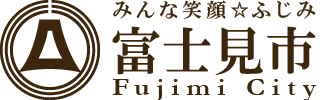児童扶養手当について
最終更新日:2025年4月1日

児童扶養手当は、ひとり親家庭等(母子家庭、父子家庭、親のいない子を養育している方)の生活の安定と、自立の促進に向けた手当を支給する制度です。
支給要件|受給できない方|支給額|支給月|所得制限|申請手続|現況届|一部支給停止|届出内容の変更
次のいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害のあるときは20歳未満)児童を監護している父または母、もしくは、父または母にかわってその児童を養育している方に支給されます。
- 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める障害の状態にある児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 船舶や飛行機の事故等により、父または母の生死が3か月以上明らかでない児童
- 婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童
- 棄児などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
(注記)事実婚とは、婚姻可能な異性と同居している場合、または頻繁に定期的な訪問と生計費の補助を受けている場合など、同居していなくても事実上の婚姻関係と認められる状況をいいます。
次に該当する場合は、児童扶養手当を受けることができません。
- 申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設や少年院など(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含み、政令で定める障害の状態にある者を除く)に養育されている、もしくは生計を同じくしているときなど
《公的年金給付等との差額併給について》
平成26年12月から公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)の給付額が児童扶養手当額を下回るときは、その差額分の手当を受給できるようになりました。
また、令和3年3月分からは、上記のうち、障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。)を受給している方は、「障害年金の子の加算部分の額」と「児童扶養手当の額」の差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。
詳しくは![]() 「障害基礎年金等を受給されているひとり親家庭の方の児童扶養手当の算出方法が見直しされます」をご覧ください。
「障害基礎年金等を受給されているひとり親家庭の方の児童扶養手当の算出方法が見直しされます」をご覧ください。
(注記)年金が受給できるようになった場合や年金の申請をした場合は、必ず届出をしてください。
令和7年4月分から手当額が以下の表のように変わりました。
| 子どもの人数 | 月額(全部支給) | 月額(一部支給) |
|---|---|---|
| 1人の場合 | 46,690円 | 46,680円~11,010円 |
| 2人目以降の場合 | 1人の場合の月額に、1人につき | 1人の場合の月額に、1人につき |
- 一部支給の手当額は、次の計算式に基づき決定されます。
- 子ども1人目・・・・・46,690-{(受給者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.0256619+10円}
子ども2人目以降・・・11,030-{(受給者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.0039568+10円}
ただし、{ }内は10円未満四捨五入
(注記)全部支給の所得制限限度額は、下記「所得制限について」の表に定めるとおり、扶養人数に応じて額が変わります。
手当は、原則、年6回の奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に前2か月分ずつ支給されます。
(注記)振込日は、各支払月の11日(11日が土日祝日にあたる場合はその直前の平日)となります。
受給資格者およびその生計を同じくする扶養義務者などの前年の所得(受給資格者が母(または父)の場合、母(または父)および児童が児童の父(または母)から受ける養育費の8割相当額を含める)が下表の限度額以上である場合は、その年度(11月分から翌年の10月分まで)は、手当の全部又は一部が支給停止となります。
| 扶養親族等の人数 | 受給者本人(父・母・養育者) | 扶養義務者・配偶者・ 孤児などの養育者 | |
|---|---|---|---|
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
| 5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
(注記)受給者の所得額は、収入から必要経費(給与所得控除など)を引いた額に、養育費の8割相当を加算した額です。
(注記)「受給者本人」の「一部支給」欄および「扶養義務者・配偶者・孤児などの養育者」欄の限度額以上の場合、手当の全額が停止されます。(一部支給はありません)
(注記)扶養親族等は税法上の扶養人数です。
(注記)所得額は、前年分の所得(ただし、1月~9月までに認定請求した場合は前々年の所得)を適用します。
(注記)給与所得または公的年金等の所得を有する方については、給与所得と公的年金等に係る所得の合計額から10万円(10万円未満の場合はその額)が控除されます。
(注記)一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
(注記)公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除があります。
手当を受給するためには申請(認定請求)が必要です。申請者の状況により申請手続きに必要な書類をご案内しますので、子育て支援課手当医療グループにお問合せください。
また、申請手続きには1時間程度かかる場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
手当は、原則として認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、11月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
平成20年4月から、児童扶養手当支給開始月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過した(3歳未満の児童を監護する場合、満3歳翌月から起算して5年を経過した)ときは、手当の2分の1が支給停止となります。ただし、受給資格者が就業しているなどの政令で定める事由に該当する間は、一部支給停止措置を適用しません。(一部支給停止適用除外事由届出書)
対象の方には、事前にお知らせが届きますので、期限までに必要書類を添付して提出してください。
各種の届出が必要となりますので、子育て支援課窓口でお手続きをお願いします。無届のまま手当を受給されていますと、手当全額を返還していただく場合がありますのでご注意ください。詳しくは、お問い合わせください。
【例】
・住所(転居)や氏名を変更したとき
・振込口座を変更したとき
・公的年金等を申請または受給できるようになったとき
・児童や扶養義務者の方と同居や別居となったとき
・婚姻(事実婚を含む)や転出などで受給資格がなくなったとき
・児童を養育しなくなったとき
虚偽の申請により不正に手当を受給した場合は、手当の返還や罰則があります
・お支払いした手当を返還していただきます。(児童扶養手当法第23条)
・3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。(児童扶養手当法第35条)
お問い合わせ
子育て支援課 手当医療グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7104
FAX:049-251-1025