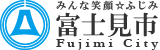9月3日は睡眠の日です。
最終更新日:2025年9月24日
睡眠の日とは、春の3月18日と、秋の9月3日の年2回あり、日本睡眠学会と精神・神経科科学振興財団が設立した睡眠健康推進機構が、睡眠や健康への意識を高めることを目的に制定しました。
9月3日 秋の睡眠の日です
秋の睡眠の日の前後1週間の8月27日~9月10日を健康睡眠週間として啓発活動が行われています。
3月18日 春の睡眠の日です
春の睡眠の日の前後1週間の3月11日~3月25日を健康睡眠習慣として啓発活動が行われています。
睡眠の役割
睡眠は、心身の健康維持に必要で大切な要素です。
睡眠には心身の疲労を回復する働きがあります。また、脳を休息・回復させる働きがあります。
ストレスや生活リズムの乱れから睡眠に支障をきたして不眠になると、日中の集中力の低下や体調不良などを招き、社会生活に悪
影響を与えてしまいます。
睡眠と生活習慣病の関係について
質の悪い睡眠は生活習慣病のリスクを高め、かつ症状を悪化させてしまうことがわかっています。
睡眠と生活習慣病の関係を知り、規則正しい生活をするように心がけましょう
健康づくりのための睡眠ガイド 2023
厚生労働省では、こころや体の健康づくりのために「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」を策定しました。
高齢者、大人、こどものそれぞれの世代で、良質な睡眠をとるための推奨事項をまとめています。
| 高齢者 | ・寝床にいる時間は8時間以内を目安にしましょう。 |
|---|---|
| 大人 | ・睡眠時間は6時間以上を目安として必要な睡眠時間を確保しましょう。 |
| こども | ・小学生は9~12時間、中学・高校生は8~10時間を参考に睡眠時間を確保しましょう。 |
お問い合わせ
健康増進センター 健康づくり支援係
〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬3351番地の2
電話番号:049-252-3771
FAX:049-255-3321