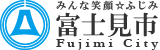教育行政方針
最終更新日:2025年2月12日
教育委員会が新年度の教育行政の執行にあたり、教育行政運営の基本方針を示したもので、毎年第1回市議会定例会にて教育長が表明します。
令和7年度 富士見市教育行政方針
はじめに
昨年は、各種イベントや事業において活躍する子どもたちの姿を通して、世代を超えた交流を感じることができました。
令和7年度も地域の皆様の協力を得て、子どもたちを見守り、育てるべく、教育行政を推進してまいります。
それでは、第3次富士見市教育振興基本計画に掲げる基本方針に沿って、令和7年度の教育行政方針を申し上げます。
1 学びあい、高めあい、夢と希望をはぐくむ教育の推進
1つ目の柱、学びあい、高めあい、夢と希望をはぐくむ教育の推進について申し上げます。
小・中・特別支援学校では、確かな学力、豊かな心、健やかな体のバランスがとれた生きる力の育成に努め、子どもたち一人ひとりを認め、励まし、ほめる教育を行うことにより、夢と希望をはぐくむ教育を推進いたします。
(1)児童生徒一人ひとりに応じたきめ細やかな指導による学力の育成
まず、児童生徒一人ひとりに応じたきめ細やかな指導による学力の育成について申し上げます。
学力の向上につきましては、指導主事による各校の課題に応じた支援や若手教員育成指導員を活用した教員の指導力向上により、主体的・対話的で深い学びとなる授業を展開し、児童生徒の確かな学力を育成します。各種学力調査結果から課題であることが明らかとなったデータ活用能力については、学力向上プロジェクトチームを活用し、改善に取り組みます。また、一人一台端末を活用した、協働的な学習や一人ひとりに合わせた学習により、友だちと関わりあいながら、自らの学びを深める児童生徒を育成します。
英語教育につきましては、英語専科教員の小学校全校への配置により、授業の更なる充実に努めます。
情報教育につきましては、情報モラル教育を充実させるとともに、小学生ロボコン大会を開催し、STEM教育で培った論理的な思考力や創造性、問題解決能力を活かす場を設けます。
読書活動の充実につきましては、計画的な図書の購入等により、蔵書の充実を図ります。
(2)多様性を認めあい、誰一人取り残さない教育の推進
次に、多様性を認めあい、誰一人取り残さない教育の推進について申し上げます。
特別支援教育につきましては、通級指導教室を小学校2校に新設するとともに、小・中学校と特別支援学校の支援籍学習を通し、児童生徒一人ひとりの個性を肯定的に受け止め、豊かな人間性をはぐくむインクルーシブ教育を推進します。また、富士見特別支援学校や特別支援教育推進プロジェクトチームの専門性を活かし、児童生徒の特性に応じた支援や教職員の資質向上を図ります。
未就学児に係る就学相談につきましては、保育施設と連携し、専任の相談員により子どもや保護者の実情に応じた支援を行います。
不登校児童生徒につきましては、出張あすなろや校内の居場所の拡充により多様な学びの場を確保するとともに、児童生徒が仲間を思いやり支えあうピアサポートの理念を通して、児童生徒一人ひとりの特性や願いに寄り添いながら、社会的な自立をめざします。また、保護者や地域の支援者を対象とした不登校支援者セミナーを実施します。
教育相談につきましては、各学校においてコーディネーターとなる教員を育成するとともに、ふじみ野小学校に移転する教育相談室を中心として、公共施設を利用した出張相談や、学校、家庭、医療機関等への訪問支援により、多面的・多角的な視点から個々の児童生徒に応じた支援の充実に努めます。
いのちを大切にする教育につきましては、道徳教育、人権教育、包括的セクシュアリティ教育の視点を加えて開発した「富士見市いのちの授業+」を実践し、自尊感情を高める教育を推進します。
いじめ防止対策につきましては、いじめのない学校づくり子ども会議における話合いを踏まえ、各学校において、子どもたち主体によるいじめ防止に向けた取組みを展開します。
小中一貫教育につきましては、児童生徒間の交流や合同の取組みのほか、教員間の研修により、義務教育9年間を見通したカリキュラムの幅を広げ、授業の充実を目指します。
(3)自らの健康・安全を守る資質・能力と健やかな体の育成
次に、自らの健康・安全を守る資質・能力と健やかな体の育成について申し上げます。
児童生徒の体力向上につきましては、敏捷性を高めるため、ラダーやラバーリングの活用のほか、縄チャレの推進により、運動好きな児童生徒の育成に努めるとともに、体力向上推進委員会における授業研究会やアスリートによる授業を展開し、児童生徒の体力の向上を図ります。
安全・防災教育につきましては、児童生徒が主体的に自他の命を守ることができるよう取り組むとともに、学校・地域が連携し、非常時には地域の一員として力を発揮できるよう意識づけを図ります。
また、スクールガードリーダーをはじめ、学校応援団や地域の皆様の協力を得ながら、児童生徒が安全に登下校できるよう取り組みます。
学校給食につきましては、富士見市産のカブなど地場産野菜の積極的な活用や郷土料理の提供により、地産地消の推進や食への関心を高めます。また、ボイラーの蒸気管更新工事など施設・設備の計画的な維持管理・更新に努めるとともに、中長期的な視点から学校給食センターの建替えについて検討します。
(4)地域の教育力を生かし教育効果を高める学校教育の推進
次に、地域の教育力を生かし教育効果を高める学校教育の推進について申し上げます。
学校・家庭・地域の連携につきましては、特色ある学校づくりをさらに推進するため、学校運営支援者協議会のコミュニティ・スクールへの移行に向け準備を進めます。
部活動の充実につきましては、地域連携に向け、受け皿となる団体などの人材確保に努めます。
教職員の働き方改革につきましては、スクール・サポート・スタッフの拡充をはじめ、業務改善検討委員会における研究成果を実践するほか、ICTの更なる活用による教職員の負担軽減について検討し、子どもと向き合う時間の確保に努めます。
学校施設につきましては、勝瀬中学校及び水谷中学校長寿命化工事、東中学校体育館改修工事のほか、富士見特別支援学校3階に教室を整備します。また、小・中学校特別教室へのエアコン設置について、普通教室のエアコン更新と併せ検討します。
ICT環境につきましては、アクセスポイントの拡充や、導入から5年が経過する児童生徒用端末の更新を進めます。
2 学びあう地域社会をめざす教育の推進
2つ目の柱として、学びあう地域社会をめざす教育の推進について申し上げます。
誰もが主体的に学習でき、学びの成果を分かちあうことで、ともに育ち、活力ある地域社会となるよう社会教育を推進します。
(1)家庭・地域の教育力の向上
まず、家庭・地域の教育力の向上について申し上げます。
家庭教育の支援につきましては、子育て世代の保護者を対象とした学習会のほか、仲間づくりや情報交換のための居場所づくりを進めます。また、地域子ども教室や青少年関係団体の活動の支援を通して、子どもの居場所づくりや青少年の健全育成に努めます。さらに、各種イベントにおいて、小・中学生が主体的に関わり、活躍できる場づくりを進めます。
(2)生涯にわたる学習機会の提供と地域づくりの推進
次に、生涯にわたる学習機会の提供と地域づくりの推進について申し上げます。
子ども大学☆ふじみにつきましては、子どもの知的好奇心を刺激し、将来の夢や希望、郷土愛をはぐくむ魅力ある講座を実施します。
家庭学習応援事業につきましては、事業を継続しつつ、これまでの成果と課題を踏まえ、実施方法の見直しに向け検討を進めます。
人権・平和教育につきましては、お互いを認め、多様性を尊重しあえる地域社会をめざし、人権問題に関する教育や啓発に努めます。またピースフェスティバルを実施するほか、戦後80年を踏まえ、戦争体験の記憶を後世に引き継ぐための取組みを進めます。
公民館におきましては、学びを通した地域づくりの核となる施設として、各地域の特性やニーズに応じ、多様な人が集い、新たな交流が生まれるよう、取組みを進めます。
全館共通の取組みにつきましては、デジタルデバイド対策としてスマホ講座の実施や、ボッチャなど誰もが楽しめるスポーツ活動の普及に取り組みます。
鶴瀬公民館では、市民の皆様との協働により子どもフェスティバルや市民大学を実施します。また、地域交流のきっかけづくりとして、関係課と連携し、eスポーツを実施します。
南畑公民館では、親子プログラミング教室などの家庭教育支援事業や、富士見高校の生徒ボランティアと連携した子ども向け事業を実施するほか、なんばた青空市場や南畑ふるさとまつりなど地域の賑わいにつながるイベントを支援します。また、びん沼自然公園等地域施設を活用した事業に取り組みます。
水谷公民館では、40回目を迎える水谷文化祭など、人と人との出会いや交流の創出に取り組みます。また、公民館をより身近に感じてもらえるよう、公民館だより500号を記念したキャラクターを発表します。
水谷東公民館では、地域の親睦と交流を図るため、やなせ川いかだラリーを開催するほか、町会、水谷東安心まちづくり協議会、ふれあいサロンの支援を通して、市民参加・協働のまちづくりに取り組みます。
(3)暮らしとまちづくりに役立つ読書活動の推進
次に、暮らしとまちづくりに役立つ読書活動の推進について申し上げます。
図書館におきましては、地域の情報拠点として幅広い市民ニーズに対応した資料を収集するとともに、公共施設での資料受け取りや電子書籍の充実により、図書館の利用促進に努めます。また、指定管理者提案事業の趣旨を踏まえ、図書館サービスの充実に向けた検討を行います。
子ども読書活動の推進につきましては、図書館と学校が連携し、中・高校生ボランティアによる読み聞かせやイベント協力を通して、読書に親しむ機会の充実を図ります。また、マルチライセンス対応の電子書籍の充実と活用に努めるほか、パパママ準備教室や医療機関において絵本を紹介し、読み聞かせの大切さを伝えます。
(4)郷土遺産の継承
次に、郷土遺産の継承について申し上げます。
市の貴重な文化財を広く知っていただくため、郷土芸能の動画配信、公共施設や商業施設における展示、遺跡見学会の実施により、文化財の魅力発信に努めます。また、難波田城跡土塁の用地購入など郷土遺産の適切な保護と活用に努めます。
資料館につきましては、水子貝塚公園の再整備に向けた基本設計を実施するとともに、令和6年度の水子貝塚発掘調査で出土した資料の整理・分析を行います。また、難波田城資料館では、戦後80年を契機として、戦中・戦後における富士見市の人びとの暮らしを振り返る企画展を開催します。
(5)開かれた教育委員会
次に、開かれた教育委員会について申し上げます。
教育委員会会議等の活性化につきましては、教育委員による学校や教育施設への訪問、研修会への参加と教育委員同士の学びあいにより、教育上の課題を把握し、教育行政への反映に努めるとともに、市ホームページを通して、教育委員活動の見える化に努めます。
おわりに
将来の予測が困難な時代において、自らが社会の創り手となり、持続可能な社会を維持・発展させていく人材の育成が求められています。
今後におきましても、自尊感情や自己肯定感を高めるとともに、人とのつながりや相手を思いやる心、社会貢献などの意識を一体的にはぐくみ、ウェルビーイングの向上に資する教育に取り組んでまいります。
引き続き市民の皆さまと議員各位のご理解とご協力をお願い申し上げまして、結びといたします。
富士見市教育委員会
教育行政方針PDF版
お問い合わせ
教育政策課 総務企画グループ
〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬1873番地1(中央図書館2階)
電話番号:049-251-2711(内線611・612)
FAX:049-255-9635