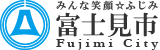家屋の評価方法
最終更新日:2025年10月1日
家屋の評価は総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定します。
評価方法については、「再建築価格を基準とする評価方法(以下「再建築価格方式(注1)」という。)」が採用されています。
新築家屋の評価
固定資産税・都市計画税の課税の根拠となる適正な評価額を求めるために、完成した建物について、屋根・外壁・各部屋の内装などに使われている資材や設備の状況を調査します。
調査方法については「![]() 家屋を新築(または増築)した場合」をご参照ください。
家屋を新築(または増築)した場合」をご参照ください。
評価額の算出
- 新築および増築分の家屋の再建築価格を求めるときは、固定資産評価基準に基づいてその家屋の部分別(屋根・外壁・基礎等)の再建築費評点数を求め合計します。
- 合計された再建築費評点数に経年減点補正率(注2)(構造・用途・種類別によって異なる。)を乗じ、最後に評点数1点当たりの価格(物価水準による補正率(注3)×設計管理等による補正率(注4))を乗じることによってその家屋の評価額を求めます。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
国の固定資産評価基準は、3年ごとに建築資材・物価等の動向を調査し、改正されます。
そのため、床面積の変更などの異動がない限り、3年間は同じ価格となります。
評価額の算出
- 前基準年度に適用した再建築費評点数に再建築費評点補正率を乗じ、現在の基準年度の再建築費評点数を求めます。再建築費評点補正率とは、前回の評価替えからの3年間の建築物価の変動率をいいます。
- この再建築費評点数に経年減点補正率を乗じて最後に評点数1点当たりの価格(物価水準による補正率×設計監理等による補正率)を乗じることによって、その家屋の評価額を求めます。
- 見直し前の評価額と見直し後(評価替え)の評価額を比較し、見直し後の評価額が上回った場合には、見直し前の評価額に据え置くこととされています。見直し前の評価額と同額か下がったときは、見直し後(評価替え)の評価額になります。
- 新評価額は3年間同じとなります。
用語の解説
(注1)再建築価格方式
評価する家屋と同一のものを今建てるとしたらどれくらいの金額がかかるかという再建築価格に、年数の経過による減価補正率(経年減点補正率)を乗じて評価額を求めるものです。
なお、再建築価格は、国の「固定資産評価基準」で定められる単価を適用して算出します。
国の基準が3年に一度見直されるため、3年間は同じ価格になります。
(注2)経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものであり、構造・用途・種類等によって異なります。
最も減価したときの補正率(減価率)は20%までとされています。
(注3)物価水準による補正率
家屋の資材費、労務費等の工事原価に相当する費用等の東京都(特別区の区域)における物価水準に対する地域的格差を考慮して定められたものです。
- 木造:0.95(地区により異なります。)
- 非木造:1.0(全市町村一律)
(注4)設計管理費等による補正率
家屋の建築費に通常含まれている設計管理費、一般管理費、利潤等の工事原価に対する割合等を考慮して定められているものです。
- 木造:1.05(全市町村一律)
- 非木造:1.1(全市町村一律)
お問い合わせ
税務課 家屋係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-251-2711(内線355・356)
FAX:049-254-6351